日本最大の労働組合の全国組織である連合は、今年の平均賃上げ率は5.46%であると発表した。これは1991年の5.66%以来の高水準だが、今の日本で景気回復や豊かさを実感できている人は少ないだろう。90年代以降、日本に格差が広がったのはなぜなのか。その原因を紐解いていく。※本稿は、前田裕之『景気はなぜ実感しにくいのか』(ちくま新書)の一部を抜粋・編集したものです。 ● 「脱成長」でマイナスなら 立場の弱い人にしわ寄せがいく 低成長期の日本が成長率を1%引き上げるのは至難の業であるのは確かだが、GDP統計を確認できる1956年度から2023年度までの68年間のうちマイナス成長を記録した年は9回だけである。この間、毎年ゼロから風船を膨らませる作業を始め、年間の最大記録を更新し続けているのだ。 風船を膨らませる担い手が減っているにもかかわらず、記録を更新している状態を「それなりの結果を残している」とプラスに評価しても良いのではないか。 もう無理に風船を膨らませなくても良いという意見もある。環境問題を資本主義経済と結びつけ、「脱成長」を説く論者もいる。しかし、現在の経済の仕組みのまま、風船を膨らませる努力をやめたらどうなるか。 仮に風船の膨らみ方を前の年に比べて10%小さくする(=マイナス10%成長になる)としよう。作業量が減るので、労働時間を減らすか人員を減らして対応するしかない。風船が膨らまなかった分だけ儲けは減る。働いている人たちの取り分は減るが、減り方は均等ではない。 戦後の日本は、風船を巨大にしてきた。前の年に比べて1%膨らませ方を抑制するだけでも大きな影響が出る。 風船を膨らませている人たちに均等に影響が及ぶのではなく、雇用保障がない弱い立場の人たちに真っ先にしわ寄せが来る傾向が強いのである。 ● 政府が描く今後10年の 実質成長率は「2%程度」 政府はどんな未来を描いているのか。内閣府は2024年1月、今後10年程度(2024〜33年度)の経済展望を発表した。 技術進歩率が回復し、女性や高齢者などの労働参加が進むと仮定する「成長実現ケース」の場合で実質成長率は2%程度、名目成長率は3%程度、現在の傾向が続くと仮定する「ベースラインケース」では実質、名目ともに0%台半ばで推移すると見込んでいる。 同年4月には2060年度までの長期試算も発表した。2025〜60年度平均の実質成長率は、最も厳しい「現状投影シナリオ」で0.2%程度、最も楽観的な「成長実現シナリオ」で1.7%程度と推計している。同年6月に発表した「経済財政運営の指針」(骨太方針)では、実質成長率1%超を2030年度以降の目標として示した。 日本とアメリカの労働生産性(労働者1人が生み出している付加価値の額)を比べると、製造業、サービス業など広範な分野で日本の生産性は低い。日本が低成長を続けているのは、生産性が低いためであり、アメリカを手本に生産性を高めよと指摘する経済学者は多い。 日本企業はもっとイノベーションを起こせ、外国から優秀な人材を受け入れよう、女性や高齢者の労働参加率を高めよう……。経済成長を促すための様々な提案に耳を傾ける価値は大いにあるが、即効薬や魔法の杖はない。 成長会計による分析から明らかなように、日本経済が今後、安定成長期に匹敵する成長軌道に戻る可能性はほとんどない。精一杯、成長する努力を続けても、今後10年間の実質成長率が平均2%に届く未来は見えない。 ● アベノミクス景気での 賃金上昇はたった一度だけ 1%前後の成長を前提(目標)に、より多くの国民が景気回復や豊かさを実感できる経済構造にするために何をなすべきかを考えるのがより現実的ではないだろうか。 日本企業の行動が日本の経済成長には必ずしも貢献していない点も改めて確認しておきたい。国内の「3つの過剰」(編集部注/バブル崩壊後、企業が抱えた設備、雇用、債務のこと)の整理にめどがついた2000年代に入っても日本企業は人件費抑制の手を緩めず、非正規雇用の割合は4割近くに達している。
コメント 10件
悲しい現実だが外国から金を奪えなくなれば国内で奪い合いになると言う事! 戦後の高度成長とバブルに至るまでの日本とバブル崩壊後の日本を考えればわかる事。 日米半導体協定とプラザ合意の影響も大きかったし小泉、竹中コンビの規制緩和も理念と現実が乖離するものだった。 ロジックとマインドのギャップが表面化と外圧をどう乗り越えるかが日本の今後の課題だと考えます。
貧困でない人は、貧困者は怠惰で高慢ゆえに貧困になっていったと考えがちです。格差を社会全体の問題として共有するなら、まずは、やむを得ない理由で貧困にならざるを得なかった人が貧困者全体のうちどの程度の割合なのか示す必要があります。他人任せで支援のただ乗りを期待していわゆる自己責任で貧困になった人達まで社会で救済するのは違和感があります。
冷戦が終わりパラダイムシフトが起こった。 それまで米ソの対立の下で儲けていた日本はソ連が倒れた後、アメリカの次のターゲットにされた。アメリカの新自由主義政策で政官財の固いトライアングルは弱体化させられ規制緩和や市場開放と言う聞き心地が良い言葉で日本経済はズタズタにされたのがこの30年間だろう。 しかしまたパラダイムシフトが起ころうとしている。アメリカの仮想敵国は中国になった。中国を倒すには日本の協力が不可欠になる。 重要度が増す日本には停滞の後の好況の時代が来る
こういった記事でいつも思いますが、日本は言われているほど「格差社会ではない」と思っています。何故なら低所得の人は、大概「独身」あるいは「親と同居」という生活スタイルを取っており、既婚子持ちの人たちに比べかなり経済的に有利な生活をしているからです。 自分が高齢になれば、不都合は出てくるでしょうが若年者にとってはまだまだ先の話であり、私は言われてるほど不平等社会ではないと思っています。
「同質性よりも人的資本の多様性を尊重する新たな雇用や社会保障制度の構築」 と 「日本型不平等社会の成立を主導してきたのは、非正規雇用を増やし、総人件費の削減を進めてきた日本企業」 って、矛盾してないか。 いろいろな立場の人がいろいろな形で働けるように、ということで労働形態の多様性を拡大してきたのに。それで格差社会になった、と言われたのではどうしていいのか分からない。 何処の国でも企業が人件費をを少なくすることで利益を増やそうとするのは当然である。 政府がやるべきことは経済効率がいい産業を振興することで収入が多い人を増やすことである。
価値観の高齢化です それを年功序列終身雇用でそれが正しいと30年変化から逃げ続けた事 少子化も高齢化の派生でしかない ただこれから解決することのない少子化やインフレで強制的に価値観を変えざるを得ない状況にこれから向き合わなければならなくなる
平等と公平はリアル世界ではあり得ないと思いますよ。 真犯人は?? アベノミクス持ち出すあたりがちょっと… まだそこ批判してるの?って感想。 経済評論家みたいな人達は偉そうに語るけど、自分達は消費増税を肯定して影響は軽微とか言っていた事を猛烈に反省して欲しい。 もし、消費税増税に反対していたならばもっと消費増税の影響を今こそ語るべきだと思う。
派遣社員を認めている事が、格差を作ってしまった。派遣社員は、いつでも解雇できる方法である。それなら正規社員より高い賃金にならないといけない。大手企業に優しい政府の対応に大きな格差問題がある。
非正規雇用を原因とされているが、自分はその前の高校、大学のシステムがおかしいのだろうと思う。多くの方が高校受験、大学受験でかなり勉強されたと思うが、進級、卒業は何ら苦労も無く社会人になったと思う。留年、中退はほぼ聞かないし、自分の周りにもいなかった。入る時に努力は必要だけど、入ってしまえばコッチのもの。会社も同じ。就職は苦労するが入ってしまえばコッチもの。 そんな教育システムは海外でも評価されない。日本で大卒でも海外では大学院で博士号取るまでいかないと大卒とは認めないと聞いた。正規雇用、非正規雇用を語る前に教育システムから変えて行かなければ、優秀な人も出て来ないし、今後もこの格差はずっと引きずるだろう。
別の観点から見るとwin95からの NET興隆に対する儲け方とも デジタル技術追求での利益回帰型と 技術非注力のダラダラ馴れ合い迎合型に 目の前に広げられてる技術仕様書に 目を通す事無く近くの誰かの解説に頼りすぎに 前を見ていたら分かる事なのに なぜか色々理由をつけて目を通さない人 だから全ての物をステレオタイプでしか 推し量れないマインドとして熟成固形化 新しい物でしか成長マージンは望めないのに なぜか第三者の成功体験をなぞる事が 自分の成功ストーリーに繋がると謎ワーク 本当に儲かる事なのかどうかの 判断能力まで欠損してるから 全ての事に反対する事で自分の住んでる世界 小さな手の届く範囲を守れると思うのでしょ 「それ嘘松!」と声を上げる事が 自分にとっての最上級の公的デジタルの 技術的運用方法なのでしょ? まぁ、それで財布がどのように太るのか 是非、実況中継希望したいです
引用: https://news.yahoo.co.jp/articles/dcb23d7e2660eb170c42a9c5e54c525272fbb427


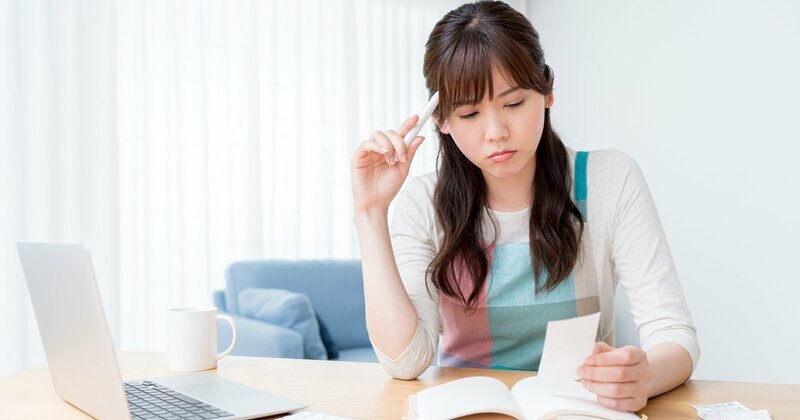


コメント